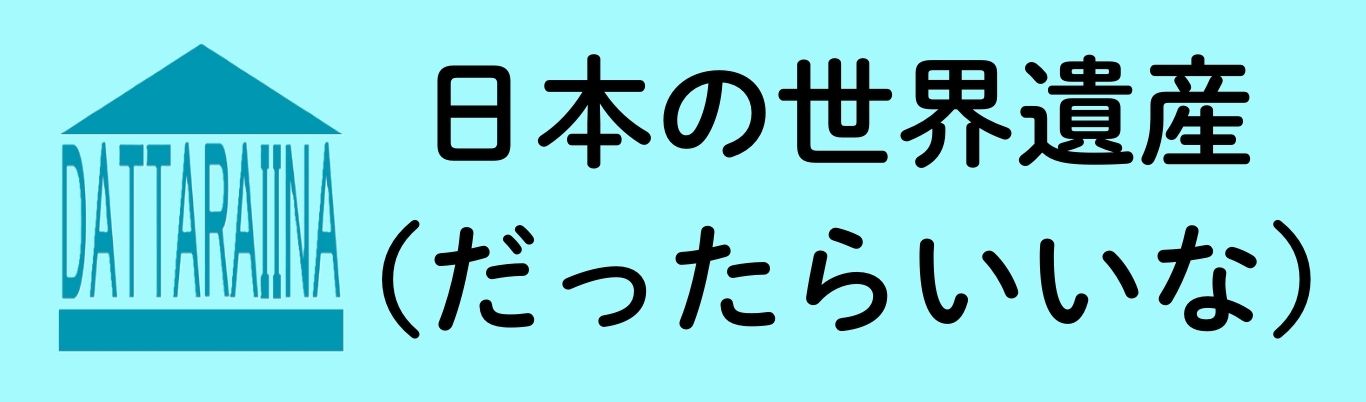「日本における海上交易の歴史」と
「日本人の海との関わり」
西日本の中央に位置する瀬戸内海は、古くから交通の往来が多い海でしたが、 時代ともに栄えた場所が変化したこともあり、現在でも近世と近代それぞれの面影を残す歴史地区が点在しています。 近世には主要な港として「尾道」のほか、潮待ちの港として「鞆の浦」などが整備され、 近代になると外国商船の交通量も増え始めたことから、 「下関・門司」や「神戸北野」といったヨーロッパの影響を受けた街区も整備されました。
また、瀬戸内海の船乗りたちは航海安全を祈願するため、 瀬戸内海沿岸近くに創建された「住吉大社」や「金比羅宮」などの神社を篤く信仰し、 島国である日本ならではの海との関わりを垣間見ることが出来ます。
瀬戸内海周辺の港町や神社群からは、 海上交通の変遷と、それらと密接に関わる信仰を知ることが出来ます。