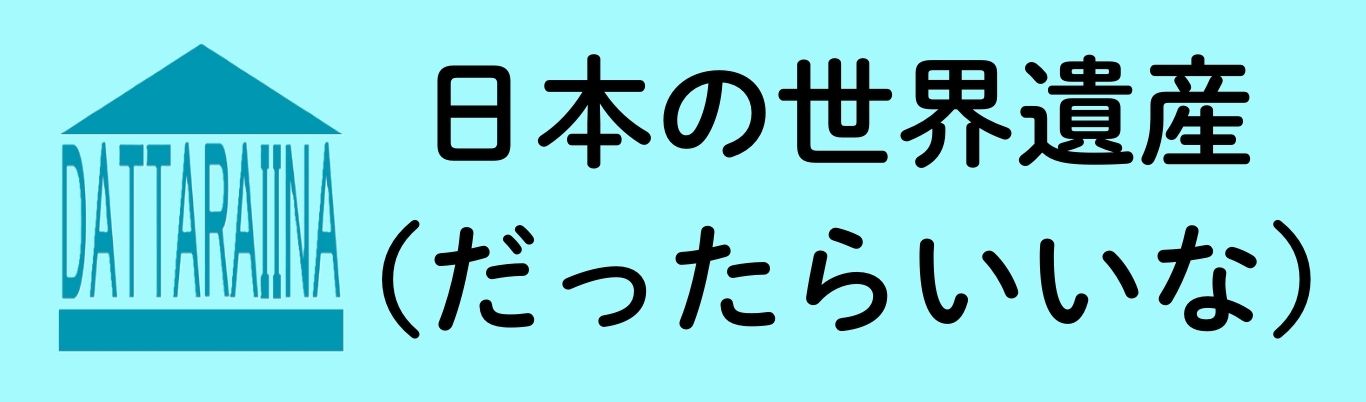「近世日本を支えた大動脈」
東海道と中山道は、17世紀から19世紀の近世日本における主要街道として、 近世日本を統治していた江戸幕府によって整備されました。幕府は 石畳の坂道や多くの宿場町を整備したほか、 治安維持や防衛といった目的から、関所や大規模城郭も沿道に多数設けました。 また、幕府特有の制度である参勤交代や 外交使節来日の際に両街道が利用されるなど、 両街道は江戸幕府の政治体制を語る上で欠かせないものです。
他にも、両街道は身分を問わず多くの人が利用したことから、 経済活動や文化芸術活動も大きく支えることになりました。
東海道と中山道に関係する文化財からは、 近世日本の政治・経済・文化芸術を多角的に知ることが出来ます。